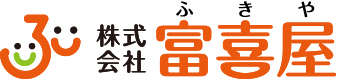孤食(こしょく)とは、家族が不在の食卓で一人で食事をすること、また家族がいても一人で食事をすることを意味しています。現在は、さまざまな原因から孤食をする人が増加しており、孤食が心身に及ぼす影響が問題になっています。
そして、こどもの“孤食”は、心身の発達にかかわる「食育」の問題としてたいへん注目されています。
好きなものばかり食べて栄養がかたより、健康や身体の発育に影響したり、家族とのコミュニケーションが少ないことで、協調性や社会性を育めなかったり、さみしさから情緒不安定になり、心の健康に影響が出る可能性があるとも指摘されています。
こどもたちの健やかな成長のためには、食事から栄養をとるだけではなく、誰かと食事を楽しむこともとても大切です。
家族構成やライフスタイルの多様化によって「孤食」は増え続けていますが、こどもたちの心と体の健康を守るために、少しでも参考にしていただければと思います。

index
7つのこ食(こしょく)とは?
「こ食」と呼ばれるものには、“孤食”のほかにも小食、個食などがあります。
そのなかの最も代表的な7つの「こ食」について説明します。また、「こ食」の逆の言葉として「共食(きょうしょく)」があります。「共食」は、家族や仲間と食事を囲むことを意味します。
1. 孤食
“孤食”は、「家族が不在の食卓で、一人で食事をすること」です。
食事中のコミュニケーションが少ないため、協調性や社会性が育たないとの指摘があります。
また、栄養バランスの偏りも気になります。

2. 小食
いつも食欲がなく、少しの量しか食べないことを“小食”と言います。もちろん、その日の体調などで食欲が出ない日もあるかと思いますが、とくにこどもの小食は、それが常態化すると成長に必要な栄養不足につながります。また、無気力になったり体力の低下も懸念されます。
3. 個食
家族で一緒に食卓を囲んでいても、それぞれ違う物を食べている状態を“個食”といいます。
コミュニケーションはとれますが、“味を共有”することができず、会話が広がりにくく協調性が育ちにくくなります。
4. 子食
こどもだけで食事をすることを“子食”と言います。
仕事などで親の帰宅時間が遅かったり、塾や習い事、アルバイト、クラブ活動などで、こどもの食事の時間が不規則になるなどが原因です。
また、こどもだけで食べるので、食事のマナーを学べなかったり、好き嫌いだけで食べ物を選んでしまったりで、健康リスクが増加するなどの懸念もあります。

5. 固食
自分の好きな決まったものばかりを食べてしまい、メニューが固定化されてしまう食生活を“固食”と言います。
同じものばかりを食べるので、好き嫌いの改善が難しく、栄養バランスも偏ります。
6. 濃食
味付けの濃いものを多く食べることを“濃食”と言います。
濃い味の食事は、塩分や糖分の摂りすぎによる生活習慣病になりやすかったり、素材の繊細な味や香り、うま味を感じ取る味覚が育ちにくくなります。近年は、うま味調味料や加工食品などを使用した、味付けの濃い食事が多いので注意が必要です。
7. 粉食
パンやピザ、パスタなど粉を使った主食を好んで食べることを“粉食”と言います。粉ものは食感が柔らかいものが多いので、よく噛まずに飲み込めるため噛む力が育ちにくくなります。
また、粉物でおなかが膨れてしまい、野菜などのおかずをとりづらいこともマイナス要素です。
7つの「こ食」以外にも
- 戸食(こしょく)
戸食とは、外食が多い食生活です。コロナ禍や忙しさから便利なデリバリー、テイクアウト等を活用したり、ファミリーレストランやファストフードが食事の定番になることも増えています。
外食は野菜不足や栄養が偏りがちになり、塩分・糖分・脂質過多で肥満につながることも。また、濃い味付けに慣れて味覚の発達に影響が出たりする可能性もあります。 - 虚食(こしょく)
虚食は、何も食べない、食欲がないことを意味しています。虚食は、栄養不足になりやすく、症状が深刻化すると摂食障害につながることも。
また、朝食を抜いたりと欠食をすると食事のリズムが体内で作れず、他の食事で大量摂取してしまい、次の日の朝に食欲が出ず、また欠食してしまうといったことを繰り返してしまいやすいです。
とくに「孤食」は、なぜ問題なのか?
“孤食”は、7つの「こ食」の中でも最も問題視されています。理由は、“孤食”は さらにほかの「こ食」を誘発することが多いからです。
結果的に以下のことが懸念されます。
食事が「空腹を満たすだけ」になりやすい(栄養バランスが崩れる)
食事の中で、好きなものだけを選んで食べてしまったり、早食いや偏食になりやすかったします。
また、不規則な食事時間になりがちです。 結果として、栄養バランスが崩れやすくなり、発育への影響や、やせ・肥満など健康への影響も懸念されます。
孤独感・不安感を感じる
“孤食”によって、孤独感や寂しさを感じやすくなります。食事を共にすることは、こどもが安心感を得たり、情緒の安定を保つ手助けになると言われています。
また楽しい食卓の記憶が少ないと、自己肯定感に影響が出たり、 孤食が日常化すると長期間にわたる“孤食”で、「人と食べるのが面倒」と感じるようになってしまうことも心配です。
協調性、コミュニケーション能力が育たたない
食事の場は、言葉のやりとりやマナー、相手への思いやりを学ぶ大切な時間です。「これ おいしいね」「この野菜なに?」など、会話をしながら食事をすることで、言語の発達や社会性、共感性、会話力、傾聴力などを、こどもたちは学ぶことができます。
しかし孤食が多くなると学びの機会が少なくなり、こどものコミュニケーションスキルへの影響が心配されます。
食事のマナーを教えてもらえない
“孤食”は、正しい食事マナーを覚える機会を減らしてしまいます。
「いただきます」「ごちそうさまでした」の挨拶や「お箸のマナー」など、みんなでご飯を食べるときに必要な最低限のマナーを覚える機会を減らしてしまいます。
結果的に、いざ他人と食事をする場面で相手を不快にさせたり、戸惑ったり、自信をなくしてしまうことがあるかもしれません。それは本人にとっても悲しいことだと思います。


“孤食”を解消する6つのアイデア
栄養バランスの偏りをはじめとした孤食による悪影響は、次のような方法で解消を目指せます。
家庭でのちょっとした工夫で、無理なく楽しい「食の時間」をつくることができます。今回は、すぐにできる6つのアイデアをご紹介します。
ご家庭のペースで、できるところから取り入れていただけたら嬉しいです。
① 休日に家族で食事をする機会をつくる
週に1回でも、家族そろって食事ができると、それが こどもにとって大切な記憶になります。
例えば、土曜日の朝は「パンとスープの日」と決めたり、日曜の夜は「みんなでカレーを食べる」という習慣をつくったり。
一緒にテーブルを囲み、会話をしながら食事をする時間が、こどもの安心感や食への興味を育ててくれます。また、一緒に食事をすることで、食事のマナーも自然と身に付きます。
② 朝食は一緒に食事をする
夜は家族の帰宅時間がバラバラで一緒に食べるのが難しいという人は、朝食を一緒に食べることから始めるのがおすすめです。毎日でなくても、週に一日だけでも、たった10分、家族で「いただきます」ができると、こどもはうれしく感じます。
簡単なトーストと果物、牛乳でもOK。「今日は幼稚園、保育園で何をするのかな?」などの会話をしながら朝の時間を過ごすだけで、元気な一日をスタートできます。
お仕事などで全員そろわないときは、一人だけでもおこさんと向き合って食べる時間を意識してみてください。
③ 食事の準備や片付けを一緒にする
休日など時間がとれるときは、一緒に作って食べられる料理を取り入れてみましょう。ホットプレートなどを使ったメニューは、家族で食卓を囲む時間が増え、ゆっくり会話をしながら食事ができるのでいいかもしれません。
他にも、「おはしを運んでもらおうかな」「サラダにトマトを盛り付けてもらおうかな」など、簡単なお手伝いから始めると、こどもの「できた!」という自己肯定感を高めることができます。
また、「自分も食事をつくった」という気持ちは、食への興味をより高めてくれます。苦手な食べ物も、自分が作ったものだと食べた、という話はよく聞きます。
準備や片付けを一緒に行うことで、食事のマナーを身に着けることもできます。
④ 冷凍食品や総菜、調理家電を活用し、食事時間を優先する
忙しい日は無理をせず、市販のものも上手に取り入れてOKです。たとえば、冷凍の野菜を使って簡単なスープをつくったり、市販のおかずに一品だけ手作りを足したり。
電子レンジ調理やホットクック、炊飯器などの調理家電も時短に役立ちます。
「作る」ことにとらわれすぎず、「一緒に食べる」ことを大切にしてみてください。
⑤ 食事の栄養バランスを整える
完璧を目指す必要はありません。「主食(ごはんやパン)」「主菜(たんぱく質)」「副菜(野菜や果物)」がそろえば大丈夫です。
朝はバナナ+ヨーグルト、昼は卵サンド+野菜スープ、夜はごはん+焼き魚+お味噌汁、など、1日単位でバランスを意識できれば十分です。
また、こどもが苦手な野菜は、みじん切りにしたり、カレーやスープに入れたり、工夫すると食べやすくなります。大人がおいしそうに食べる姿を見せることも、非常に効果的です。
小さいころは、好き嫌いがあって当たり前です。食べられなくても、食卓に出して食材に触れる機会を作ってあげることが大切です。


⑥ 遊びや絵本など、食事以外でも食べ物について触れる経験を増やす
食べ物に親しむのは、食卓だけではありません。
「にんじんさんはどこから来たの?」「お味噌はどうやってできるの?」などの絵本を読んだり、ままごと遊びでお料理ごっこをしたり、買い物に行ったときに「今日はどれが新鮮かな?」と一緒に選んだりするのも良い経験になります。
野菜を育ててみるのもおすすめです。自分で育てたものを食べると、食べる喜びもひとしおです。
こどもの「食べる力」は、日々の小さな経験の積み重ねで育っていきます。
大切なのは、完璧を目指すのではなく、できることを「楽しんで続けること」。
ご家庭でも、あたたかい食の時間が過ごせるといいですね。


味覚の基礎は、3歳までに “ある程度 形成されます”
赤ちゃんは、味覚を持って生まれてきます。
特に基本的な「甘味、苦味、酸味、塩味、うま味」などの味に反応します。
- とくに、離乳期(5〜6ヶ月ごろ)〜3歳頃に、たくさんの味や食材を経験することで、その子の「味の記憶」が形成されていきます。
- またこの時期は、「味覚の感受性」がとても高いので、どんな味に慣れ親しんだかで、その後の「好き嫌い」や「食の好み」に大きく影響します。
でも、心配しないでください! “3歳で味覚が固定されてしまう” ことはないです
- 3歳以降も、食の経験は積み重なり、味覚はどんどん成長し変化していきます。
- 小学生になるころには、少しずつ「苦味」や「酸味」などの複雑な味も楽しめるようになります。
- さらに大人になってから、好き嫌いが変わることもよくあります。
※こどものころはピーマン嫌いだったけど、今は好き など。 - 3歳までが、とっても重要なスタートラインであって、ゴールではないということです。


保護者の方に、ぜひ意識していただきたいこと
食べ物の好き嫌いを克服するには、苦手意識を軽減したり、楽しい雰囲気で食事をするなどの工夫が大切です。
- 同じものでも調理法や味付けを変えてみる
- 無理に食べさせず、楽しい食の体験を大事にする
- 苦手なものを少しでも食べられたときは思いっきりほめてあげる
- 親や周りの人がおいしそうに食べるところ見せる
- 一緒に作ってみる、食材に触ってみる(安全な範囲でお願いします)
大人たちが美味しそうに食べる姿を見せてあげるのは本当に大切なことだと思います。
また、「食べなくてもOKだよ」という空気をつくったり(プレッシャーをかけない)、食べたか 食べないかよりも「チャレンジしたこと」そのものを褒めるなど、食べることにポジティブなイメージを持ってもらうことが大切です。
ぜひ、ちょっとした成功体験をどんどんこどもたちに積ませてあげてください。