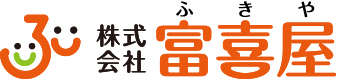淡泊でクセがなく、炒め物やスープなどさまざまな料理に使いやすい鶏肉。日本には弥生時代の初め頃に鶏(にわとり)が伝わり、古墳時代には卵を取り、その後、卵を産まなくなった鶏を食べることが一般的になりました。
江戸時代には鶏を育てることが広まり、戦後には「ブロイラー」などの肉用鶏が登場。今では手軽に食べられる食材として親しまれています。
現在では保育園や幼稚園でも、煮物やつくね、汁物などに使われ、子どもたちに親しまれています。

index
鶏肉の旬
鶏肉は通年流通しており、特定の旬はありません。
鶏肉の栄養
鶏肉は良質なたんぱく質を含み、ささみやむね肉は脂肪が少なめでヘルシーです。
おいしい「鶏肉」の選び方
肉質が鮮やかで厚みのあるものを選びましょう。
パック売りはドリップが少ないものが鮮度の良い証拠です。
鶏肉の調理のポイント
ここで保育園・幼稚園の子どもたちが「鶏肉」を美味しく食べられるように調理のコツについてお伝えします。給食やご家庭で活かしてみましょう。
鶏肉の下ごしらえ
- ドリップを拭き取る
クッキングペーパーで余分な水分を拭き取ると臭みが軽減します。 - 常温に戻す
調理前に15~30分ほど室温に置くと、均一に火が通りやすくなります。季節や肉の厚みによって調整しましょう。
鶏肉の部位に合わせた調理法
鶏肉は部位ごとに食感や味わいが異なるため、それぞれに合った調理法を選ぶと、より美味しく仕上がります。
【調理例】
- むね肉(脂肪が少なく淡泊)
⇒ カツ・蒸し鶏など - もも肉(ジューシーでコクがある)
⇒ 照り焼き・鍋物・カレーなど - ささみ(柔らかく脂肪が少ない)
⇒蒸し物・フリッターなど


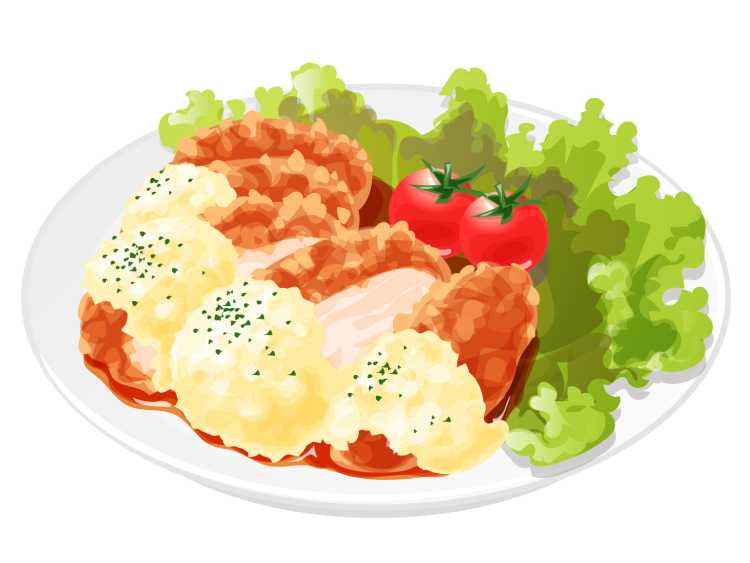





鶏肉の保存方法
次に、鶏肉の保存方法をご紹介します。
冷蔵保存
購入した鶏肉をすぐに使用する場合は、パックのまま冷蔵庫で保存し、パッケージの期限内に消費します。
冷凍保存
長期保存する場合は、お好みの大きさにカットして冷凍用保存袋に入れ、冷凍庫で保存します。保存期間の目安は約1カ月です。
解凍について
冷凍した鶏肉は、冷蔵庫で自然解凍するのが基本です。こうすることでドリップが少なくなり、うま味や食感を保つことができます。カットして使う場合は、半解凍の状態で包丁を入れると扱いやすくなります。
「鶏肉」を離乳食に取り入れる時期と硬さの目安
鶏肉は、脂肪の少ないささみや鶏むね肉は離乳初期(5、6ヵ月)から試せます。白身魚や豆腐に慣れたら開始しましょう。初期や中期は茹でてからみじん切りにしてすりつぶし、ペーストにします。片栗粉でとろみをつけたり、じゃがいもやかぼちゃを混ぜると食べやすくなります。
保存した食材を離乳食・幼児食に取り入れる場合
赤ちゃんは細菌に対して抵抗力が弱いため、冷蔵保存したものは当日、冷凍保存の場合で1週間を目安になるべく早めに使い切りましょう。幼児の場合でも、冷蔵保存で数日、冷凍保存で2週間以内が目安です。また、食べさせる前には、必ず再加熱してから与えます。
※赤ちゃんの発育・発達には個人差があります。
はじめて与える場合は、平日の医療機関が開いている時間帯がおすすめです。お子さんの様子をみながら、少量から離乳食を進めてください。

子どもに話したい「鶏肉(とりにく)」の話 ~鶏肉クイズ~
次のうち、鶏肉の「むね肉」はどの部位でしょうか?
- 背中
- 胸
- 足
答え: 胸
鶏肉の「むね肉」は胸の部分で、脂肪が少ないため、淡泊な味わいが特徴です。ちなみに、首の部分は「せせり」、足のほうにあるお肉は「もも肉」です。ほかにもいろんな部位や名前があるので、調べてみるのも面白いですね。
まとめ
鶏肉は高たんぱくで、子どもの成長に役立つ食材です。また、脂肪が少ないささみや鶏むね肉は離乳初期(5〜6ヵ月)から取り入れられる食材です。白身魚や豆腐に慣れたら、少しずつ鶏肉も試していきましょう。



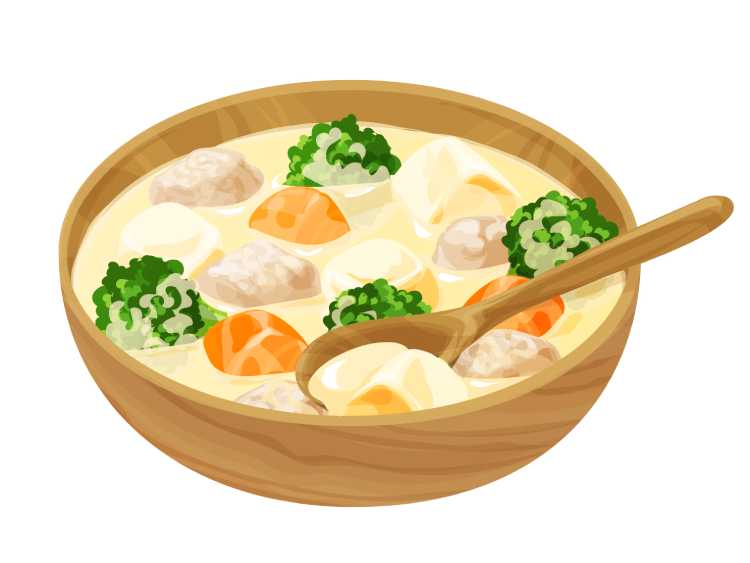

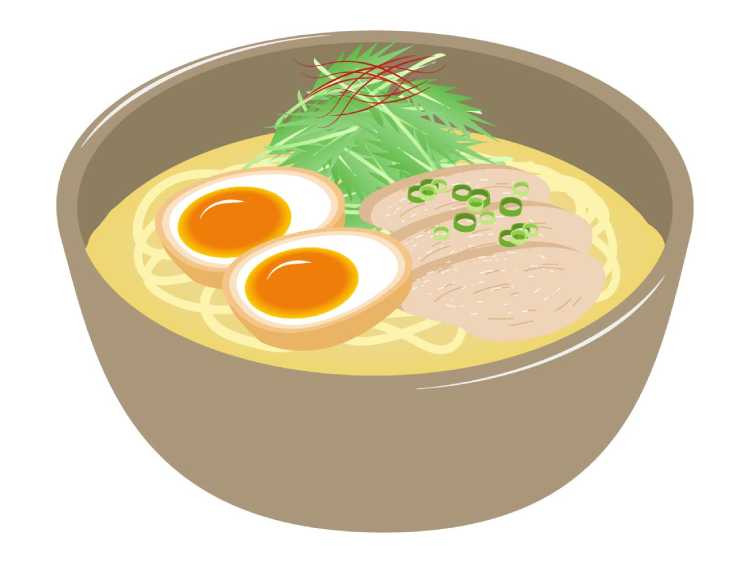






「鶏肉(とりにく)」を使ったレシピのご紹介